第一章 転生
俺の名前は安達廉太郎。27歳、無職。正確には元無職だ。なぜなら昨日、トラックに轢かれて死んだからである。
そして今、俺は鏡を見つめながら困惑していた。鏡に映っているのは間違いなくドナルド・トランプの顔だった。オレンジ色の肌、特徴的な金髪、そして誰もが知っているあの表情。
「What the hell…」
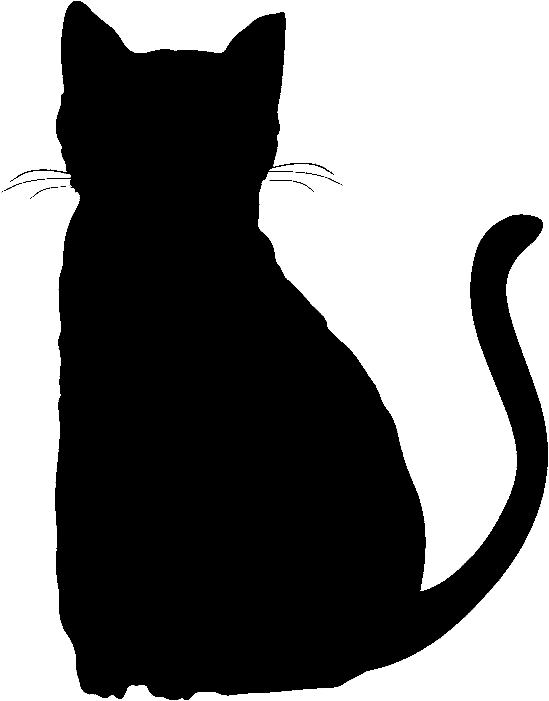
小説家・神楽木アキの創作ブログです。
医学、グルメ、法廷、ファンタジーなど幅広いジャンルの小説を執筆しています。
新人賞や公募にも挑戦中!読んでいただけると嬉しいです。
俺の名前は安達廉太郎。27歳、無職。正確には元無職だ。なぜなら昨日、トラックに轢かれて死んだからである。
そして今、俺は鏡を見つめながら困惑していた。鏡に映っているのは間違いなくドナルド・トランプの顔だった。オレンジ色の肌、特徴的な金髪、そして誰もが知っているあの表情。
「What the hell…」
十月の午後、渋谷のスターバックスは平日にも関わらず人で溢れていた。窓際の席でMacBook Airを開きながら、私はまた恋愛記事の締切に追われていた。画面に映る空白のWordドキュメントが、まるで私を責めるように白く光っている。
「25歳女性が知っておくべき、理想の男性の見つけ方10選」
クライアントから送られてきたタイトルを見るたび、胃の奥がキリキリと痛む。フリーランスライターとして独立して三年。生活費を稼ぐために、こういう「量産型恋愛コンテンツ」を月に二十本は書かなければならない現実がある。大学の社会情報学科で学んだ知識も、ジェンダー論や社会心理学の理論も、結局はネットの片隅で消費される薄っぺらい記事のネタになってしまう。
キーボードに指を置いたまま、私は深いため息をついた。理想の男性?そもそも理想って何だろう。愛って何だろう。恋愛関係の本質について、私たちは本当に理解しているのだろうか。
「1. 年収600万円以上の安定した職業」
指が勝手に動いて、ありきたりな項目を打ち込む。書きながら自分でも嫌になる。こんな記事に何の意味があるというのだろう。
「ヒカリちゃん、また難しい顔してる」
突然声をかけられて、私は顔を上げた。隣の空いていた席に、大学時代の同級生である美咲が座っていた。手にはトールサイズのアイスコーヒー。秋だというのに冷たい飲み物を選ぶ彼女の性格は、学生時代から変わっていない。
「美咲?なんでここに?」
「この近くでクライアントとミーティングがあったの。偶然にも程があるよね」
彼女は外資系コンサルティング会社で働いていて、いつも忙しそうにしている。今日もネイビーのスーツを着こなし、完璧にセットされた髪型で、いかにもできるビジネスウーマンといった風貌だ。学生時代から美人だったが、社会人になってさらに洗練されている。
「ちょうどよかった。ちょっと聞きたいことがあるの」
私はMacBookの画面を少し彼女の方に向けた。白いドキュメントには、先ほど書いた「年収600万円以上」という一行だけが寂しく表示されている。
真の商人は先も立ち、我も立つことを思うなり
—石田梅岩『都鄙問答』より
享保十九年、秋。朝霧が堂島川の水面を這うように流れる刻限に、播磨屋伊之助は米会所への石畳を踏みしめていた。二十二の若さで既に家業の一翼を担う身でありながら、彼の胸に宿るは父祖伝来の商法への静かなる反逆心であった。
「おはようさんどす、若旦那」
石橋のたもとで声をかけてきたのは、同じく米会所へ向かう近江屋の手代である。伊之助は軽く会釈を返しながら、その男の背に負われた帳面の厚みに目をやった。堅実な商いを重ねる老舗の証拠であろう。だが、それこそが伊之助には古臭く映るのであった。
堂島米会所の正面に立つと、既に朝一番の取引に備える商人たちの熱気が伝わってくる。ここは天下の台所と呼ばれる大坂にあって、なお格別の存在である。諸国の大名が米を換金する蔵屋敷が立ち並び、全国の米価がここで決まる。そして何より、世にも珍しき「帳合米」という、実際の米を動かさぬ取引が行われる場所なのだ。
伊之助の目は、会所の奥で繰り広げられる激しい手振りと怒号に釘付けになった。あれこそが、父源右衛門が「博打同然」と眉をひそめる先物取引である。だが伊之助には、それが新時代の商いの姿に見えて仕方がなかった。
ささ……さら……さら……
あなたの指先が白い紙の上を這う。ペンの先端が紙面に触れる瞬間の、あの微細な摩擦音。
ささ……さら……さら……
北川澪は患者記録に向かい、今日も同じリズムで文字を刻んでいく。病院の心理カウンセリング室は午後の陽光に満たされているが、彼女の内側はひんやりとした静寂に包まれている。
「田中雅彦、32歳、反復性悪夢症候群……」
ささ……さら……
ペン先が紙に触れるたび、澪の鼓膜に微かな振動が伝わる。HSP——高感受性者——として、彼女はあらゆる音を皮膚で感じてしまう。同僚の足音、空調の唸り、患者の息遣い。すべてが彼女の神経系を直接刺激する。
つ……つ……つ……
壁時計の秒針が、澪の意識を一秒ずつ削り取っていく。
り……り……り……
電話のベル音が、澪の睡眠を切り裂く。
午前4時17分。デジタル時計の赤い数字が、暗闇に浮かび上がる。
澪は受話器を取る。
「はい……」
「先生、助けてください」
声の主は田中雅彦だった。しかし彼の声は、電話線を通じてではなく、澪の内側から響いてくる。
り……り……り……
電話は鳴り続けている。澪はもう一度受話器を取る。
「北川先生ですか?」
今度は山田花子の声。
「私の中の田中が、暴れているんです」
澪は受話器を見つめる。電話線は壁から抜けていた。